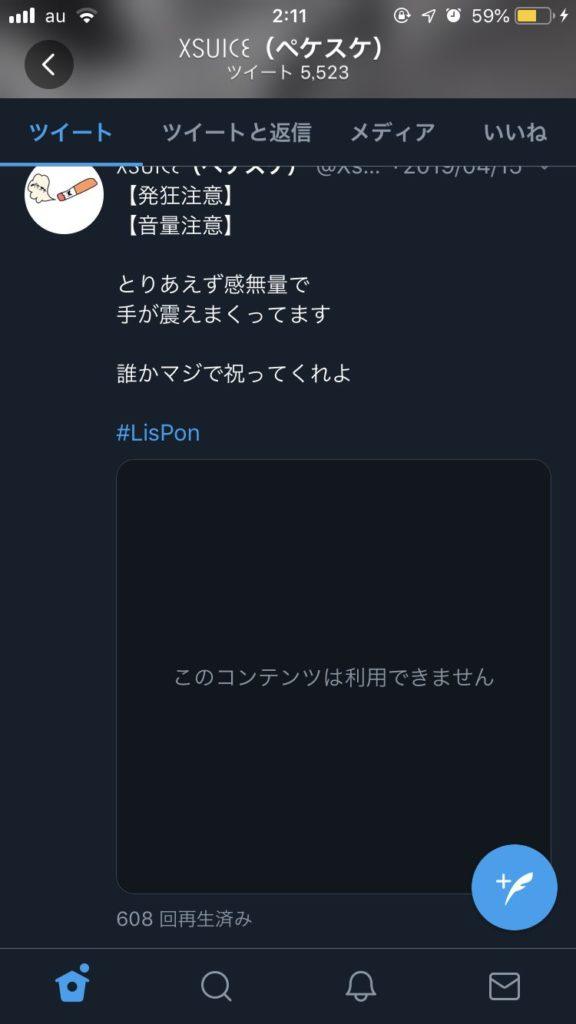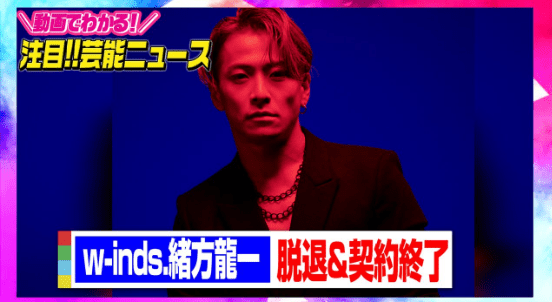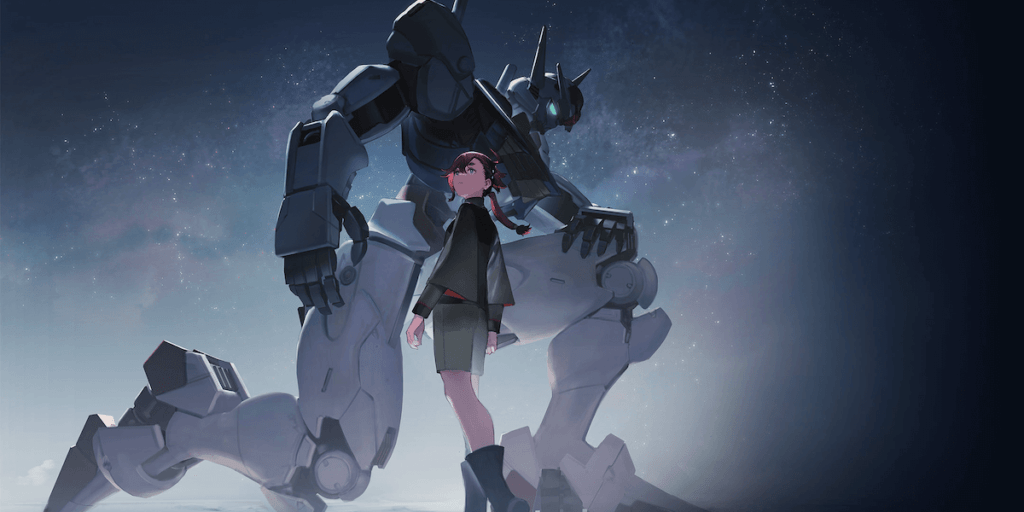東電 13 兆 円 自己 破産
東電 13 兆 円 自己 破産: 「株主代表訴訟」とは、この時期に東京電力の経営陣に対して行われた訴訟にちなんで名付けられたものです。これは、「会社の所有者である株主」から「会社の損害賠償」で「個人役員」が訴えられている場合です。 株主は会社の所有者です。ちなみに、標準的な民事の場合、査定される印紙税は、合計金額のパーセンテージに基づいて計算されます。通常の民事訴訟で13兆円の補償金を請求する場合は、100億円以上の切手手数料が必要です。ただし、この合計はまったく準備できません。 一方、株主代表訴訟の場合、前提条件が満たされていれば、臨時訴訟が提起される可能性があります。これは、13,000円の印紙税を支払うことで、何兆もの補償があった場合でも行うことができます。 この設計の理由は、株主代表訴訟によって提供される報酬は、訴訟の原告である株主ではなく、会社に支払われるためです。この設計により、会社は全額の報酬を受け取ることができます。経営成績の悪さの結果として会社が被った損失を補うために、自由に使える個々の管理資産を使用してください。 その結果、企業価値が高まり、株主は企業価値の上昇による株価上昇という間接的な報酬を受け取ることになります。役員が株主代表訴訟で敗訴した場合、会社の資産ではなく、家や土地などの個人資産を処分したとしても、補償金を支払わなければなりません。 彼が会社の資産を使って補償金を支払うことができたとしても、これは事実です。債務が返済されない場合、多くの将来の請求書が取り戻され、債務者は破産します。 2011年に東日本大震災が発生した際、東京電力の旧経営陣は「大津波の襲来を事前に予測することは可能か」と質問した。 「事前に浸水対策などの事故防止対策を実施することは可能ですか?」 総額22兆円の補償を求める5つの元経営陣が東京電力に対して提起した株主代表訴訟の最初のラウンドで、裁判所は元東京電力経営陣に対して非常に厳しい評決を下した。 東京地方裁判所の朝倉義英裁判官(54歳)は、2002年に政府機関がまとめた長期評価に基づく15.7メートルの津波推定値は「合理的な科学的信頼性のある知識」であると認めた。それが必要だということ。 これは、長期評価に基づいて見積もったためです。彼は津波を防ぐために何もしなかったが、後に「安全に関する知識と義務感が根本的に不足していたことを述べなければならない」と認めた。 しかし、「空虚さ」の感覚は、受け取った補償額に比例して増加します。日本で最も裕福な人の名前は約3兆円ですが、彼らが働いている企業の所有者ではないサラリーマンの経営者は13兆円を支払う余裕がありません。 会社の個々の役員が負担する責任をカバーすることができる「会社役員賠償責任保険」(「D&O保険」としても知られている)として知られているタイプの保険があります。ただし、この種の保険は、放射能汚染や地震や津波などの自然災害などの特別な損害補償を伴う場合のために予約されています。 あなたは何の責任も負わない可能性があります。 MS&ADのような大手損害保険会社でも、D&O保険の最大保険金額は約10億円であり、13兆円以上の保険金が下がることは非常に疑わしい。そもそも。 株主代表訴訟で求められている補償額は「13兆円」で、非常に巨額の金額です。大和銀行のニューヨーク支店で1995年に発見された大規模な損失事件をめぐって提起された株主代表訴訟は、司法制度の歴史の中で最も重要な事件の1つです。事件は1995年の事件の発見を中心にした。 株主の権利擁護チームの事務局長を務める前川拓郎氏によると、東京電力は会社の債務を回収する努力を強いられているという。ただし、前経営陣が法廷で破産保護を求め、免税を請求する許可を与えられた場合、債務は返済されません。 さらに、債務を回収するために、東京電力は前の経営陣に代わって破産を申請するオプションがあります。しかし、前の経営陣が破産申請に従わないと言っていたので、そうなる可能性は非常に低いです。 当時、柏崎柏原子力発電所のタービン建屋の開口部は、洪水を防ぐために水密化されており、2年ほど前から同様の予防策が講じられていたと考えられます。彼は事故が防がれたかもしれないという結論に達し、4人の過失が発生の直接の原因であると述べた。 小森明夫氏の宣言によると、元常務は悲劇の約8ヶ月前に推計結果を知っていたため、損害賠償責任を負わなかった。その結果、彼は経済的責任を免除されました。 請求された合計金額は、補償として承認された金額から差し引かれました。補償金として承認された金額には、廃止措置費用約1兆6,150億円、被害者補償額約7兆8,334億円、除染費用約4兆6,226億円が含まれています。 その後、考えてみて、それぞれの欠陥が存在するかどうかを判断します。推定報告を受けた2008年7月に原子力・立地副総裁を務めていた武黒氏は、「対策を講じずに放置された怠慢は極めて不合理で容認できない」と批判した。同じ部門のゼネラルマネージャーとしての地位を受け入れた。さらに、「措置を講じずに放置された不作為は、非常に不合理で容認できない」と述べた。これに加えて、私は自分が間違っていたことを認めました。 日本の電力部門は、総力戦(太平洋戦争)に備えて1939年に国有化されました。 1951年、米国と連合国の占領軍の要請により、民営化され、特定の地域に1つずつ、9つの民間所有の政府認可独占企業が誕生しました。これには東京電力が含まれます。 [13] [14]ビジネスモデルは、当時主に規制され、個人的に管理されていた米国の電気産業で使用されていたものに基づいています。 1950年代、同社の主な目的は、第二次世界大戦によって基盤となったインフラストラクチャに与えられた破壊からの迅速な回復を可能にすることでした。復興期を経て、国の急速な経済成長に対応するため、企業は供給能力を増強する必要がありました。これは、化石燃料を使用する発電所と、より効果的な送電網の建設によって達成されました。 1960年代から1970年代にかけて、同社は環境汚染のレベルの上昇と石油価格の変動によってもたらされる課題に対処するのに苦労しました。東京電力がLNGを燃料とする発電所のネットワークを拡大し、原子力発電への依存度を高めることは、東京電力が環境問題に取り組むための最初のステップでした。 1971年3月26日、福島第一原子力発電所の最初の原子力発電所(別名福島I)は、運転可能な容量で発電を開始しました。 1980年代と1990年代には、エアコンやその他のIT / OAアプライアンスが広く使用されていたため、昼間と夜間の電力需要に違いがありました。東京電力は、余剰発電容量を削減し、稼働率を高めるために、揚水発電設備を開発し、蓄熱ユニットを推進しました。これは、これら2つの目標を達成するために行われました。